11月1日(金)
みなさま
ごまー
にほんブログ村のサブカテゴリーを少し変更しました。
「ベース」から「ギター」に変更しました。
どうかクリックお願いします!
↓↓↓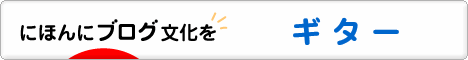
あなたの1クリックで確実にランキングが上がります!
何卒宜しくお願い致します。(懇願 )
)
最近はギターいじりばっかりしていて、今後もギターの記事を書くことも多そうなので変更してみました。
本当は「ベース」にも引き続き参加したいのですが、サブカテゴリーは3つまでしか設定できないので仕方ありません。
私の場合、ベースはエレキ、すなわちベースギターでありギターの一種なのでオッケーということで…
では早速、ギターのネタを書きます。
書店でヤング・ギター11月号を立ち読みしました。
とっくに発売されてるものですが、今頃気付いて立ち読みしました。
付録DVDはガルネリウスのSyu、そしてコンチェルト・ムーンの島紀史という贅沢な内容ですが…
この2人は、もういいかなってカンジです。
そのDVDに他には、グレン・プラウドフットという新しめのギタリストも収録されてます。
私の知らない名前ですが、記事を見るとなんやら物凄い怪物ギタリストだそうで、物凄く気になってきました…
買ってしまいました
グレン・プラウドフット。
こんな人です↓
あまりテクニカルな人には見えません。
しかしDVDを見たら、ビッキリ魂消ました!
バカテク大好きっ子の私ですし、今まで散々バカテクを見てきましたからそう簡単には驚きませんが…
百聞は一見にしかずです。
とりあえずYouTubeから強烈なのをチョイスして貼っておきます↓
Glenn Proudfoot - "Betcha Can't Play This" 1 - 4 Linked
Glenn Proudfoot - Monster Licks No: 1
マイケル・アンジェロ以来の衝撃です。
一体何を食べたらこんなに弾けるようになるのでしょうか?
さて、前回の記事の専門学校時代に作ったストラトですが…
早速ナットを作り直すべく、おとといナット材を買いに行きました。
アメリカ村のイシバシ楽器へ行ったのですが、少ししか種類を置いてないですね。
ギターマンのしか扱ってなくて、オイル漬け牛骨ナットが欲しかったのですがありませんでした。
それに私はギターマンのパーツはあまり好きではありません。
仕方なく普通の牛骨、しかも漂白タイプしかないのでそれを購入しました。
漂白タイプは真っ白で見た目がプラスチックみたいで安っぽく見えるのが嫌なんです。
ついでに弦も購入。
やっぱり09-42のゲージの方がネックに優しそうなので、次の弦交換でこっちに替えます。
(実はトラスロッドが締める方向にほぼ限界まで来ているので…)
では、ナット製作に取り掛かります。
まずは弦を外しますが…
段ボールに切れ目を入れて弦を挟んでおきます。
ちょっとした知恵で、弦が絡まなくて良いです。
付いているナットを外します。
外すことを前提に少量の接着剤で軽く接着されているので、ハンマーの衝撃で簡単に外れます。
塗料がナットにまで差し掛かっている場合は、塗装が欠けるのを防ぐためナイフで切れ目を入れておきます。
フェンダー・タイプの場合はヘッド側から当て木をして叩きます。
反対側から叩くと、ナットより先の指板が欠けてしまう恐れがあるので…
外れました。
溝の底に接着剤が残っていれば、丁寧に取り除きましょう。
指板にはまる厚さにまで削ります。
大抵ナット材はサイズに余裕があり、今回の場合は0.2mmほど削らないとはまりません。
歪んだり削り過ぎたりしないよう、ノギスで測ったり現物合わせをしながら慎重に削っていきます。
しかし、横幅(長さ)はほぼ丁度でした。
もしボートネックだったら、完全に長さが足らないではないですかっ!
(いや、ボートネックって厚みがあるだけで、ネック幅は普通でしたっけ?)
いずれにせよギターマンさん、ナット材はもう少し長めに作って下さい!

溝の底に合うようにナット底部にアールを付けます。
底部のアール加工が済んだ時点で接着してしまう人もいますが、私はギリギリまで接着せずに進めます。
(何故なら、溝切りで失敗したらまた外さないといけないのでっ )
)

上面のアール加工をします。
この際なので、ヘッド表面の塗装もすることにしました。
元々ポリウレタンで塗装したのですが、20年以上経ってもあまり変色せず白っぽいままなのがカッコ悪いので…
クリアラッカーを吹きます。
ラッカーなら経年で焼けたりクラックが入ったりすると思うので…
ラッカーの吹き付けは最低でも7~8回は重ね塗りしたいので、その間はナット製作は中断。
塗装の合間に、指板のスキャロップドを1つ増やすことにしました。
18フレット以上だけをスキャロップドにしてたのですが、17フレットもスキャロップドにします。
普段なら面倒でやろうとしない作業ですが、この勢いに任せてやってしまいます。
それにしてもスキャロップド加工をするのは、実に20年ぶりぐらいですのだ。
単4電池をパット代わりにしてペーパーで削っていきます。
ポジションによってくぼみのカーブが異なるので、身の回りの物とかで合うものを探して利用してみましょう。
フレットを傷付けないように、必要ならばマスキングして行います。(私は傷付けまくってますが…)
たった1フレット分だけなのにかなり時間がかかってしまいました。
手前の18フレットのスキャロップドが若干浅いので、あとで修正しようと思います。
さて、2日かけて塗り重ね&乾燥させたヘッド表面を水研ぎします。
ペーパーの600番で平面を出し、800、1000、1200、1500、2000番と番手を上げてペーパー傷を取っていき仕上げます。
カエルさん手伝い中
ありがとうございます。
水研が終わったらバフ掛け。
コンパウンドで手バフです。
テカテカに艶が出たら完了
ペグとストリングガイドを取り付けます。
やっとナット製作の続きに戻ります。
いよいよ弦の溝切りです。
溝切りで私が使っているヤスリ一式です。
ギターで使うのは左の細い2本と一番右の目立てヤスリの計3本です。
真ん中の太めの3本はベース(一番太いのは5弦用)の溝切りで使います。
目立てヤスリで6本の溝を罫書き(けがき)ます。
もちろん罫書きの前に鉛筆で下書きしておりますよ。
弦の太さを考慮せず単純に等間隔で罫書くと、1~6弦へ行くに従いだんだん弦間が狭くなっていく仕上がりになります。
間隔を「弦の中心で捉える」or「弦の輪郭で捉える」かによって違ってきますので、そのバランスが難しいところです。
私の好みでは両者の中間ぐらいでバランスを取ってますが、今回は見た目重視で弦間を同じに揃えることにします。
丸棒ヤスリで各ゲージに合った太さの溝を削ります。
3~1弦になると一番細い丸棒ヤスリでも太いので、先の細い部分を使ったり目立てヤスリで行います。
溝には弦がペグポストへ向かうように傾斜を付けなければなりません。
傾斜がないとナット溝内でビリついたりチューニングが狂いやすくなったりします。
逆に傾斜がきついと接点が点になるので摩耗が早くなります。
何度も深さを確認しながら少しずつ慎重に削ります。
2フレットを押さえながらナットとの間の弦をトントンと叩いて1フレットでの隙間を見ます。
ここが完全に着いてしまって隙間がなくなると、解放でビリついたり音詰まりをしてしまいます。
深く削り過ぎた場合、削った粉を瞬間接着剤で固めて充填するという誤魔化し方もありますが、お薦め出来ません。
またナット材を買ってきて、潔く一から作り直しましょう。
溝切りが出来たら、私はようやくここでネックに接着します。
ナットの底部にごく少量の瞬間接着剤をツン、ツンと2ヶ所に着けて接着します。
量が多すぎたり側面にも着けてしまったりすると、次の交換時に外れにくくて難儀します。
接着したら、最後に全体の整形の仕上げをします。
表面を磨いて艶を出してもいいのですが、漂白牛骨だと真っ白でプラスチックに見えるのであえてペーパー掛けで終了。
完成しました↓
ぱんぱかぱーん

やっぱり無漂白の方がいいですのだ
せっかく時間かけて作ったのに、なんだかモヤモヤが残ります。
完成記念写真です↓
わーい、あはははは…
カエルさんが邪魔でギターが見えませんが、手伝ってくれたので全然オッケルです。
まー。
■先月(10月)の買い物 O.S.T. 『リーサル・ウェポン3』
O.S.T. 『リーサル・ウェポン3』  ザ・ポリス 『白熱のロック・オンステージ! ザ・ポリス①』
ザ・ポリス 『白熱のロック・オンステージ! ザ・ポリス①』  アンヌ・ドゥールトミキルセン 『サイレント・タイム』
アンヌ・ドゥールトミキルセン 『サイレント・タイム』  ザ・ポリス 『白熱のロック・オンステージ! ザ・ポリス②』
ザ・ポリス 『白熱のロック・オンステージ! ザ・ポリス②』  V.A. 『MUSIC CAMP 2010 ~green side~』
V.A. 『MUSIC CAMP 2010 ~green side~』  レインボー 『闇からの一撃』
レインボー 『闇からの一撃』  レインボー 『レインボー・オン・ステージ』
レインボー 『レインボー・オン・ステージ』  イングヴェイ・マルムスティーン 『トライアル・バイ・ファイアー:ライヴ・イン・レニングラード』
イングヴェイ・マルムスティーン 『トライアル・バイ・ファイアー:ライヴ・イン・レニングラード』  MILES DAVIS 『NORTH SEA JAZZ LEGENDARY CONCERTS』(CD+DVD)
MILES DAVIS 『NORTH SEA JAZZ LEGENDARY CONCERTS』(CD+DVD)  ビル・エヴァンス 『クレスト・オブ・ア・ウェイヴ』
ビル・エヴァンス 『クレスト・オブ・ア・ウェイヴ』  オーネット・コールマン 『ツインズ』
オーネット・コールマン 『ツインズ』
ランキングに参加しています

↑どうかカエルさんをクリックして下さいませ (←懇願)
(←懇願)
↧
ストラトのナット製作、指板のスキャロップド加工をしました。
↧